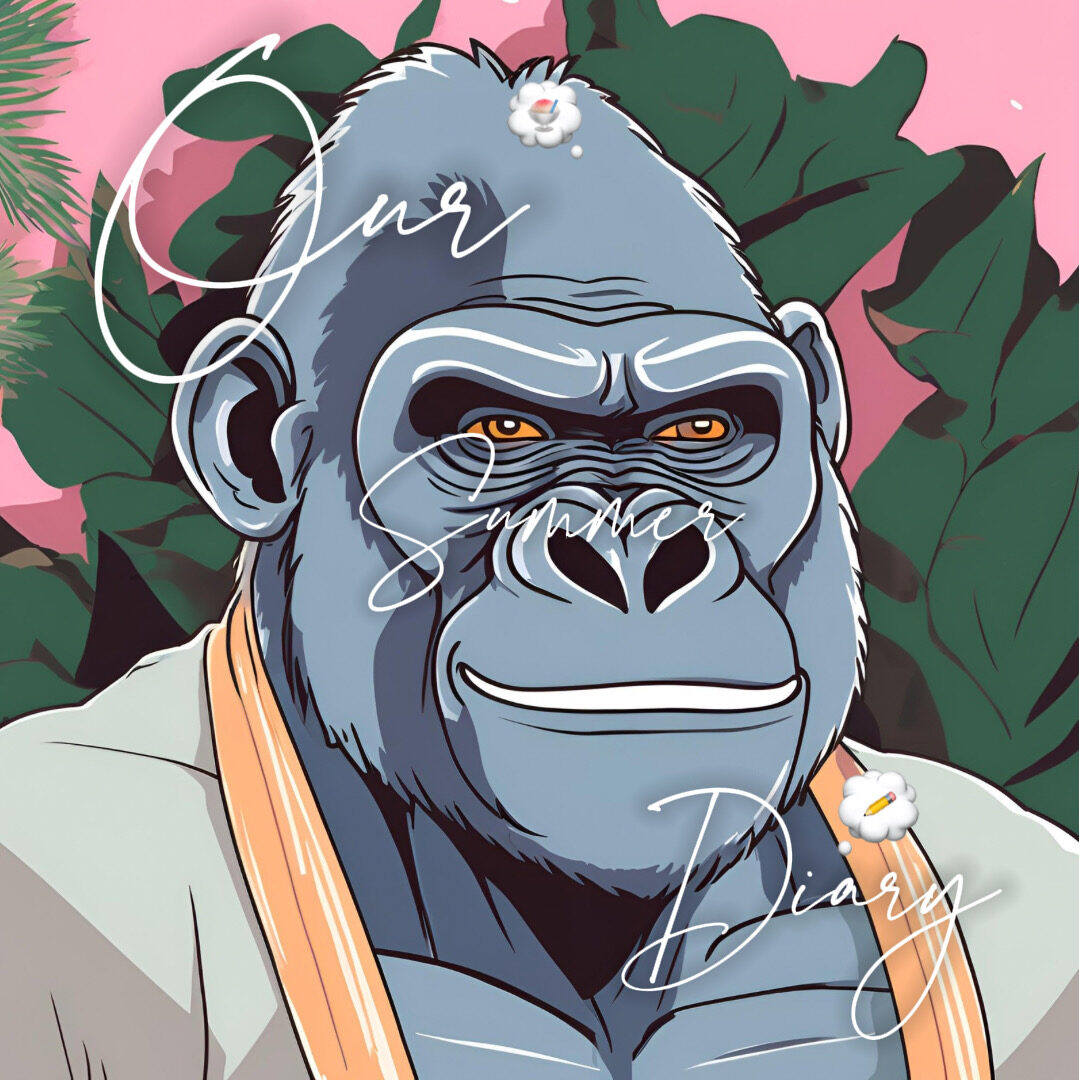不登校など様々な理由で十分な義務教育を受けられなかった子どもたちのために教育機会を確保するための法律で2017年に施行されました。それにともない同年、文科省も基本方針を策定し通知も出しております。
そもそも憲法第26条ですべての国民がその能力に応じて、等しく教育を受けられる権利が定められていますよね。その権利を保障するために、教育基本法をはじめとした義務教育に関するさまざまな法律が整備されているはずですので必然だと思います。
それでは、この教育機会確保法(正式名称:義務教育の段階における普通教育に相当する機会の確保等に関する法律)の基本理念を紹介しますね。
①すべての子どもたちが安心して教育を受けられる学校環境の確保
②不登校の子どもそれぞれの状況に応じた支援
③不登校の子どもが安心して十分に教育を受けられる学校環境の整備
④年齢・国籍を問わず能力に応じた教育の確保
⑤国・地方公共団体・民間団体などの密接な連携
そして、重要視されているポイントとして「子どもの最善の利益」を最優先に支援することを改めて確認するとともに、支援の際に登校という結果のみを目標にするのではなく、子ども自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを重視しています。
これらが法律上のお話です。先生方、まずくないですか?
私の経験上のお話で恐縮ですが、2022年に実施した教職員研修で以上の法律について問うたところ、法律自体ご存じの先生は3割にも達していませんでした。施行から5年後ですよ(泣)。そして学校現場では旧態依然とした生徒指導が蔓延っている状況。(もちろん自己研鑽され、職員室内で旧態と闘い、奮闘されている先生方も多くいらっしゃいます!…比較的、若い先生が多いのはなぜでしょう?)学校は組織です。皆さんが思ってらっしゃる以上に管理職の色によって良くも悪くもなり得るのです。法律を読み込み理解し、そんな実践家の教員を育成しようとっしている学校長はいかほどいらっしゃるんでしょう。
決して学校批判や管理職批判がしたいわけではありません。その上には教育委員会…地方自治体…。監視管理はなんのため?首長の評(票)価集め。自治体間のけん制し合い。
子どもを政治に巻き込まないでいただきたいものです。