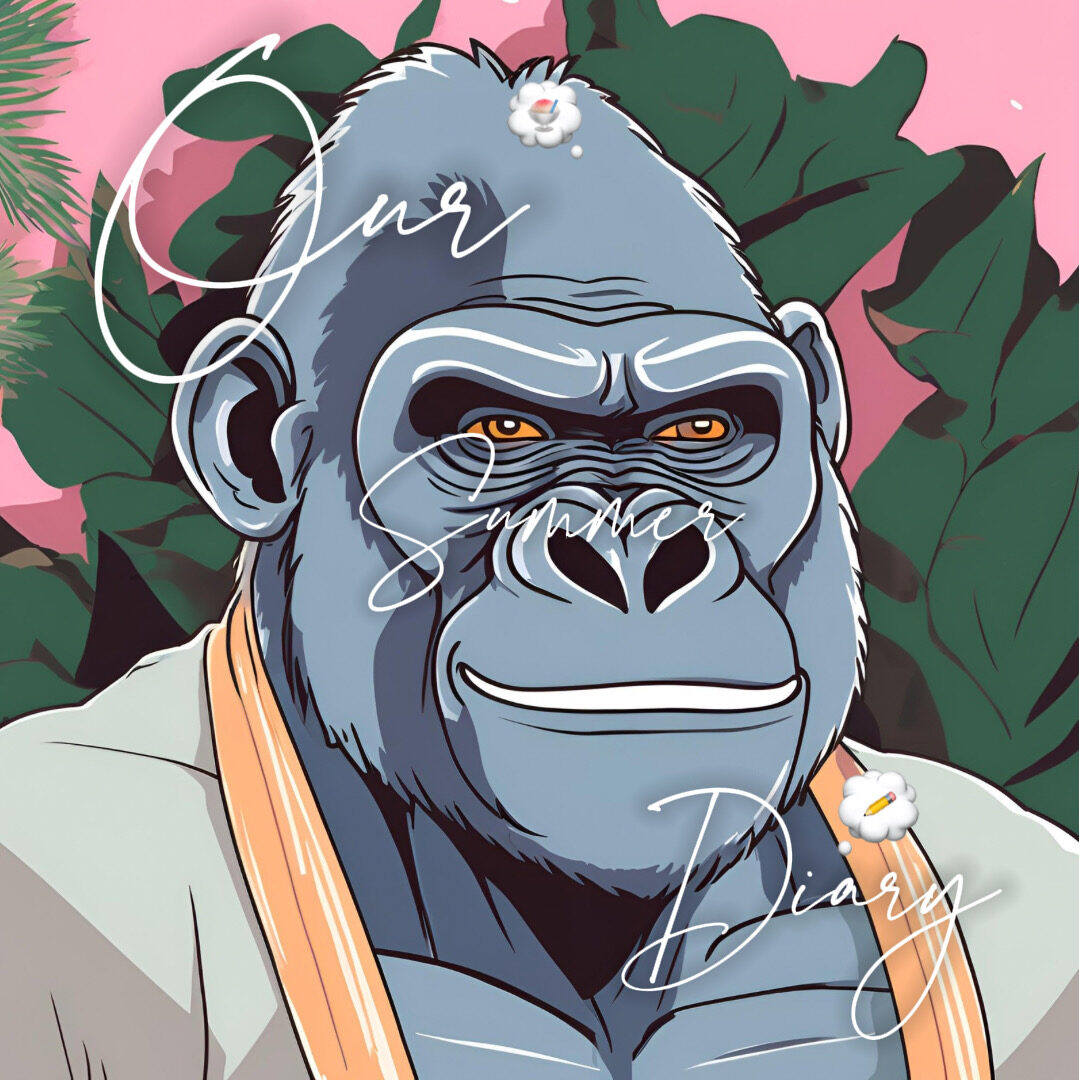小学校2年生時、担任の先生の学級王国作りからはみ出された子のお話。発達特性があり、厳しい先生の指導と折り合いがつかず泣きわめく毎日…離席する…追いかけまわる。雨の中運動場に逃げ回る…追いかけまわる。給食が食べることが怖い…学校は個別支援と称して、階段下の廊下で給食を食べさせる。そんな毎日を過ごす中、家で母親に「学校が怖い。」とやっと洩らすことができた。
母親はしばしの間、学校との関係を良好にするために理解を得ようと努められましたが、学校からは常に最後は「でもね…」「だからね…」と諭される日々。連絡帳に特性を理解した上での対応を書いたことも一度や二度ではなかったとのことです。結局、学校は諦められました。
そして私との出会い。子どもは子どもらしく無条件でかわいい。確かに特性は見受けられましたが、すぐに仲良くなることができ、小さなコミュニティに入ることから不安や緊張、人と関わることの良さを感じてもらうことにしました。うちに通い始めて日に日に自分らしさを出せるようになりました。小さなお兄さんやちょっと大きなお姉さんたちと横の関係や斜めの関係の中で、「ありがとう」と言えるようにもなり、逆に「ありがとう」と言ってもらえる体験もすることができました。安心。
さて大変なのはお母さん。そりゃそうですよね。学校と離れたところで自分らしさを取り戻した我が子を見る喜びと同時に、学校に対する怒りや恨みつらみが増大してくるジレンマ。苦しいですよね。私に出来ることは先ずは以って寄り添うこと。傾聴はもちろんします。共感もします。代弁もします。方向づけもします…しかし、頭では感情移入はしません。アセスメントとプランニングを脳みそフル回転でします。面談の日の目的は安心して笑って帰ってもらうことです。
さてさてそこからが本当の私のお仕事。対局している二者。対立構造になってしまっている構図をどのように溶解していくのかがお仕事です。伝達役ではなく通訳役です。管理職の児童理解の不足。発達特性や心理、保護者理解の不足に同じ教師として泣ける思いでした。私の力量の無さです。結局、2年生の間は学校に行くことはありませんでした。もちろん学校復帰がすべてとは全く思っていません。(ここは後日、機会があれば詳しく)しかし、私の思いは2年生という学齢での学力保障です。
裏技です。3年生になる前に次の担任の先生を暗に指名させていただきました。(もちろん校内人事は校長の権限ですから)…新しい先生に確信していました。詳細は長くなるので割愛しますが、3年生から学校復帰。本人も保護者も色々なことがりながらも充実した毎日を欠席なしで過ごされました。
4年生を経て、現在5年生。
「学校が怖い」「先生が怖い」…という日々。…学校の役割って何なんでしょうか。教師の専門性とは何なんでしょうか。先生の育ちから持ち備えた〝ものさし”で子どもたちは計られていいのでしょうか。