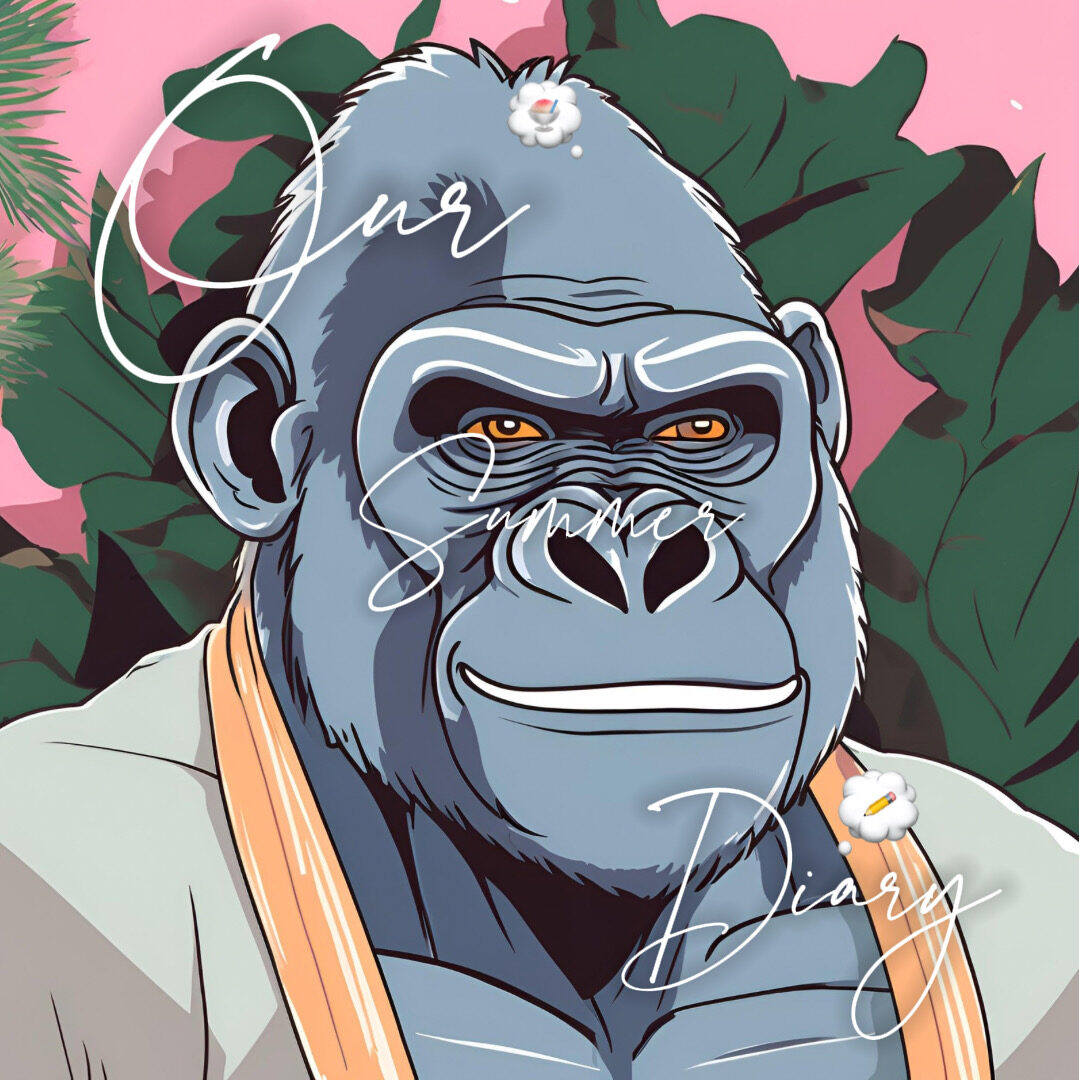長期の不登校状態。もう6年目になります。小学校の時のいじめがきっかけで不登校になりました。本人にとっては「学校に行きたくても、学校に行けない。」…つらい心境です。いじめの構造については、いつかお話したいと思いますが、本日は、この親子のお話です。
6年間。長いですよね。誰もがイメージするであろうこの6年間は、本人をはじめ保護者の方にとっては、我々のイメージする何倍も何倍も長い6年間です。毎日毎日、「明日は…明後日こそは…」と苦悩し続けての6年間なのです。学校に登校していることが何気なく当たり前になっているご家庭には、想像だにできない期待と絶望の繰り返しの時間です。そして、不登校の子にとっては、辛いことがありながらも何気に当たり前に学校で過ごしている子どもよりも、孤独に学校のことを考えている量と時間が多いのです。時間単位ではなく何分単位です。誰よりも学校行事の予定について詳しいです。「なぜ自分は外に出れないのか?自分に勇気がないからなのか?…」どんどん自分を責めてしまいます。そして、「なぜ行けないのか?」は、「なぜあの時に行かなかったのか?」と、過去の自分をさらに苦しめてしまいます。自分の理想像と現在の自分に乖離が生じ、どんどん現在から目を背けたくなってしまいます。
一方、保護者の方はどうでしょう。学校に復帰してほしい。その願いは当然です。初めは誰かのせいにしてしまいます。闘うエネルギーは長続きしません。そこから解決しないことへの焦りを感じ、次はご自身を責めてしまいます。絶対に悪くないにもかかわらず…。ここからが親子間の齟齬が生じ始めてきます。保護者の方にはもちろん悪気など微塵もありませんが、微妙に表出する焦りや不安、期待、絶望、そもそも注目が子ども本人にとっては痛々しいほど伝わるのです。決して保護者の方を批判しているわけではありません。家庭というコアな空間では距離と時間が近いので当然のことなのです。それほど、過敏な子ほど繊細で傷つきやすいということです。理想と現実のズレ、先述した本人の心理的な時間軸とのズレ等が、残念ながら親子間のバトルを生じさせてしまいます。
さて、私の役割は?微力ながら長年寄り添わせていただかせている私は今日、どんなお話をお聞きし、どんなお話をさせていただいたでしょう。また機会があればお伝えいたします。
貢献のプライドに渾身あるのみ